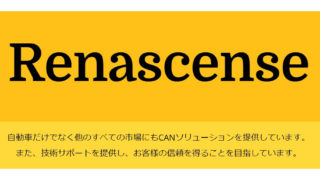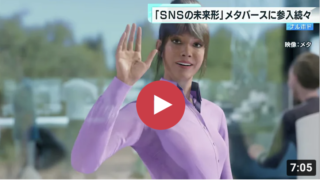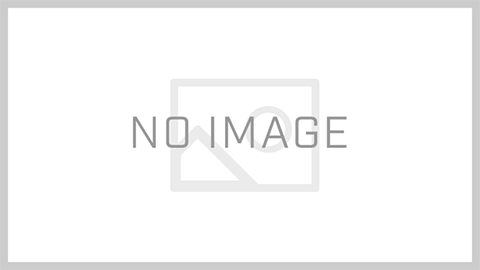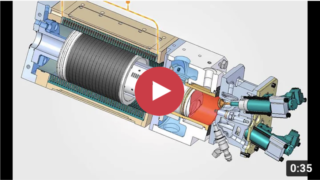ブロックチェーン技術を活用することで、コピーが容易なデジタルデータに対し、唯一無二な資産的価値を付与し、新たな売買市場を生み出す技術として注目を浴びている「NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)」。中には数億円の価格が付くデジタルアート作品も登場している。今回は、ブロックチェーンコンテンツ協会代表理事もつとめる国光宏尚氏への取材と合わせて、NFTの基礎知識、暗号資産との違い、国内外のNFTマーケットプレイス、なぜデジタルデータに数億円といった価値が付くのかなどについて徹底解説する。

<目次>
- NFTとは何か? 何が革新的なのか?
- NFTが注目を集めるようになった背景
- NFTと暗号資産は何が違うのか?イーサリアムとの関係は?
- NFTの持つ3つの特徴
- どうすればNFTを購入・販売できるのか?
- 国内外の主要マーケットプレイス
- NFTにまつわる4つの懸念点とは?
- NFTは「新しいコンテンツ流通」の血液となるのか
NFTとは何か? 何が革新的なのか?
NFTとは、「偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ」のこと。暗号資産(仮想通貨)と同じく、ブロックチェーン上で発行および取引される。従来、デジタルデータは容易にコピー・改ざんができるため、現物の宝石や絵画などのような資産価値があるとはみなされなかった。
この状況を変えたのがブロックチェーンだ。ブロックチェーン上のデジタルデータは、参加者相互の検証が入ることでコピーや改ざんをしにくくし、デジタルデータの資産価値を持たせられるようになった。ビットコインが数百万円でやり取りできるのは、この仕組みのおかげだ。
これまでも、デジタルデータに電子透かしを入れるなどの方法はあったが、コピーや改ざんを直接防ぐ技術はこれまでなかった。デジタルデータに唯一無二の価値を持たせることを可能にしたのがNFTなのである。
NFTの出現に期待できる分野は多い。デジタルアートはもちろん、ゲームやマンガ、デジタルジャケットの限定版などは利用が期待できる。
國光氏によれば、「物理的なものの管理や資産価値の証明、たとえば不動産の証明書などにも活用できるが、わざわざNFTを使う必要がない。デジタル資産やデジタルアートなどに対する証明でこそ、NFTの真価を発揮できる」という。

世界最大のマーケットプレイスOpenseaに出資するgumiの創業者で、ブロックチェーンコンテンツ協会代表理事もつとめる国光 宏尚氏
NFTが注目を集めるようになった背景
NFTの歴史は、2017年にイーサリアムブロックチェーン上で誕生した「CryptoKitties」というゲームに端を発する。しかし、急速に注目を浴びだしたのは2021年に入ってからだ。2021年3月には、Twitter創業者のジャック・ドーシー氏の出品した同氏の初ツイートが約3億円で落札。
テスラのイーロン・マスク氏が出品した音楽作品には約1億円の値が付いた。日本人では、VRアーティストのせきぐちあいみ氏が出品した作品が約1,300万円で落札されるなど、話題に事欠かない状況が続いている。
NFTの代表的な取引サービスとして知られる「OpenSea」。2021年1月に約8億円だった月次取引高は、翌月2月には約100億円と急速に成長した。
従来は資産価値の付与が困難だったデジタルデータがNFTにより資産的価値と売買市場が形成されたことにより、アート界隈で注目を集めるようになった。さらに、上記で紹介したような高額での取引が実際に行われたことなどから、急速に注目を集めている。
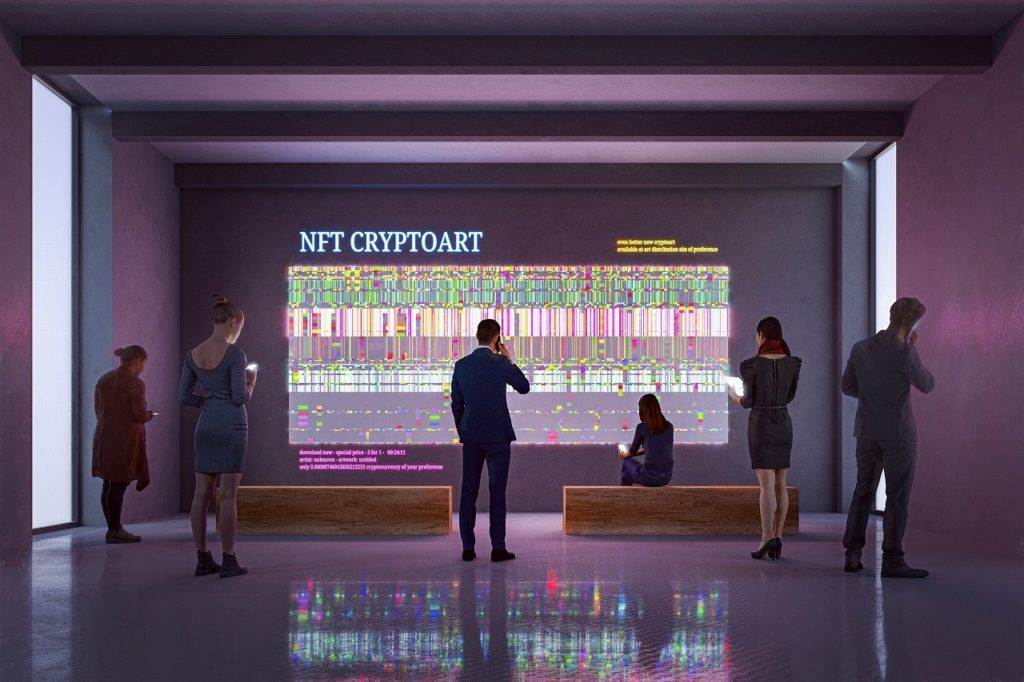
デジタル資産に革命をもたらすNFT
(Photo/Getty Images)
NFTと暗号資産は何が違うのか?イーサリアムとの関係は?
NFTと暗号資産の違いは、端的に言えばトークンが代替性か非代替性かどうかということである。暗号資産は、FT(Fungible-Token:代替性トークン)であり、資産個別の識別情報を無視して「〇〇万円分の資産価値を持ったデジタルデータ」として扱うことで、他の暗号資産や現金と交換できる。つまり、暗号資産は代替可能なトークンだ。
一方、NFTは各作品の識別情報も踏まえて資産価値を与え、他の同等作品とは交換できない唯一無二の存在として扱う。したがって、同じようなデータでもまったく異なるし、その金銭的な価値は相対取引によってのみ決まるケースも多いだろう。芸術作品などとの相性が良いのはこうした理由からだ。
また、イーサリアム(ETH)は、ヴィタリック・ブテリン氏によって開発されたプラットフォームの名称だ。ここで使用される仮想通貨はイーサという名称だが、日本では、プラットフォームとイーサをどちらも「イーサリアム」と呼ぶケースが多い。
現在、NFTの取引の大半はこのイーサリアムブロックチェーン上で取引されている。イーサリアムはプラットフォームになっているが、オープンソース・ソフトウェア・プロジェクトのため、中央で管理する者がいないのも特徴だ。NFT市場の過熱に合わせて、プラットフォームとしてのイーサリアムも仮想通貨のイーサも評価を高めている。
一方で、NFTで注目を集めているがゆえに競合の台頭も著しい。国光氏によると、「イーサリアム以外のブロックチェーンプラットフォームプレイヤーが出そろってきた。今後はこのプラットフォーム同士の戦いが始まる。かつての検索エンジンやECサイトで見られた競争と同じことが起こるだろう」という。
| 名称 | 暗号資産 | NFT |
| 特徴 | 代替可能トークン | 非代替性トークン |
| 意味 | 同じトークンが存在する | 同じトークンが存在しない |
| 分割 | 可能 | 不可能 |
| イーサリアムでの規格 | ERC20 (ERC1155) | ERC721 (ERC1155) |
| 活用領域 | 通貨やポイントなど数量的なもの | デジタルアート、ゲームアイテムなど、1点もの |
NFTの持つ3つの特徴
NFTの持つ特徴は、大きく分けて3つある。それがプログラマビリティ・取引可能性・相互運用性だ。
1.プログラマビリティ
プログラマビリティとは、2次流通で手数料が入るなど、さまざまな付加機能をそのデータ自体に付与できるということだ。 その好例となるのが、転々流通時の手数料だ。ある絵画を画家から購入した画廊が、顧客にその絵画を販売したとしよう。画廊から顧客に販売する際、画家には収入が入らない。しかし、NFTなら作者の手を離れても、「転々流通時に購入代金の一部を支払う」というプログラムを仕込むことできる。
そのため、1次創作者に継続的にマージンが入る仕組みを作ることもできるし、著者権管理を行う中間団体(たとえば音楽で言うとJASRACのような団体)が存在しなくても済むことになる。
転々流通はあくまでプログラマビリティの要素の1つに過ぎないが、「今後は従来の物理的な取引では想像もつかない仕組みが構築される可能性がある」(國光氏)という。この特徴はNFTの持つ特徴の中でも最も重要な要素と言えるだろう。
2.取引可能性
NFTは、オーナーシップが特定のサービスベンダーではなく非中央集権的なブロックチェーン上に明記されている。このため、所有者は、ビットコインなどのように、所有しているNFTを自由に移転できる。このことを「取引可能性」と呼ぶ。
これにより、国や既存の枠組みにとらわれることなく、従来以上に自由な取引が可能になる。
3.相互運用性
NFTの仕様は、現在のところ共通規格として定められているため、この規格に沿って発行するサービスなら、どこでも取り扱うことが可能だ。
なお、NFTを扱うイーサリアムブロックチェーンの規格は、ERC721が一般的である。ただ、現状、技術的に相互運用性は完全ではなく、この規格が必ずしも標準というわけではない点には注意が必要だろう。
参照:Fin Tech Journalより